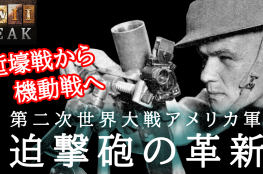YouTube動画「アメリカ軍の傑作銃M1カービン開発秘話」(2025年7月4日公開)で、動画の尺や構成の関係上触れることのできなかった情報を含めてご紹介します。
はじめに
第一次世界大戦後のアメリカ軍では、歩兵の兵器体系の強化に取り組みます。1936年には、30口径のライフル弾を連続射撃可能な自動小銃M1(ガーランド)が採用され、歩兵小銃隊への配備が進められました。一方で、第一線で任務にあたる兵士のうち、敵との近接戦闘を主任務とせず、必ずしも重い小銃を携行しない職種である将校、下士官、砲兵、車両搭乗員、後方支援部隊などの兵士には、自衛火器として拳銃が支給されていました。
しかし、欧州で勃発した第二次世界大戦では、歩兵の火力向上が著しく、機動戦で後方においても敵との不規則な遭遇が予想される新しい戦争の時代を迎えるなかで、兵士たちにとって拳銃より強力で、かつ軽量の自動火器を装備する必要性が浮き彫りとなりました。後にアメリカ軍の歩兵用火器では第二次世界大戦で最も多く生産され、戦後も長く活躍するカービン銃として生まれることになる新型軽小銃(New Light Rifle)の開発は、そのような事情を背景に始まりました。
開発の経緯
従来の拳銃は有効射程が短いうえ、有効な射撃をおこなうための習熟も困難で、効果的な自衛火器とは言えない事情がありました。そして、ヨーロッパにおけるドイツの電撃戦のように、新しい時代の戦争においては、後方においても敵のパラシュート部隊等との遭遇戦が発生することを想定し、拳銃よりも迅速かつ正確に多数の目標に対処できる自衛火器として、新型軽小銃が求められたわけです。
アメリカ軍における新型軽小銃の開発は、1940年10月頃に軍需省兵器局によって開始されました。開発目標は、拳銃の限界を克服し、同時に軽量で扱いやすい連続射撃可能な自動火器です。このときの目標性能は、重さが約5ポンド(約2.3キログラム)未満、有効射程300ヤード(約270メートル)というものでした。
新型軽小銃の開発に向けて、1940年12月に、まずは使用する弾薬の仕様が決定されました。30口径カービン弾です。この新しい弾薬は、標準的な45口径の拳銃弾よりも威力があり、より遠距離での命中精度が高いのが特徴です。
兵器局は、これら銃と弾薬の仕様を国内の主要な銃火器メーカーと開発者に送付し、新型軽小銃開発を促します。翌1941年5月、兵器局は複数の業者から試作銃の提出を受け、予備的な試験を実施、いずれも要求仕様に対応しているとして、4ヶ月後の同年9月には、アバディーン性能試験場で実用試験を実施することになりました。
実用試験には6種類の新型軽小銃がエントリー
実用試験には、オートオードナンス社、ハリングトン&リチャードソン社(設計者ユージン・G・ライジングを含む)、ウッドハル社、ハイド社、サベージ社、そしてスプリングフィールド造兵廠(ウィンチェスター社の設計)からエントリーされた6種類の試作銃が試験されました。
試験では、射撃精度、信頼性(ダストテスト、泥テスト、水没テストなど)、耐久性、重量、取り扱い、連射速度、整備性など、多岐にわたる評価が行われました。特に、重さ、取り扱い、連射速度が評価の主要な要素でした。精度については、100ヤードで4インチ四方の的に確実に命中させる能力が求められました。
試験対象となった6種類の試作銃のうち、最終的にスプリングフィールド造兵廠が提出したウィンチェスター社設計のモデルを採用することが決まりました。ウィンチェスター社の試作銃は、他の候補と比べて最も軽量であること、部品点数も少なく安価であり、信頼性と生産性の両方で優れていることが評価されたためです。
わずか2週間でつくられたウィンチェスター社のプロトタイプ
実は、このウィンチェスター社の試作銃が開発されたのには、面白いエピソードがあります。ウィンチェスター社では、もともとガーランド自動小銃の後継モデルを開発していたため、当初は新型軽小銃の試験にはエントリーしていませんでした。しかし、1941年5月の予備試験で、各社から提出された設計案に満足できなかった兵器局は、ウィンチェスター社が開発を進めていた新型自動小銃をさらに軽量化してカービン銃を試作することを依頼します。これを受けてウィンチェスター社では、わずか2週間でプロトタイプをつくりあげ、9月の試験に間に合わせたのです。
第二次世界大戦で最も多く生産された火器に
こうして採用が決定された新型軽小銃は「U.S. Carbine, Caliber .30, M1」として制式化され、日本軍の真珠湾攻撃を1ヶ月後に控えた同年11月に、最初の製造契約がウィンチェスター社との間で結ばれました。
対日戦争の勃発で、第二次世界大戦に本格参戦することになったアメリカ軍では、M1カービンの本格生産を開始します。同時に各部の改良と、様々な任務に応じた派生モデルの開発もおこなわれました。銃床を折りたたみ式にしてより携行性を高めたM1A1、フルオート射撃に対応したM2、暗闇でも射撃可能な赤外線暗視装置に対応したT3(戦後にM3として制式化)などがあります。これらの派生モデルを含めたカービン銃の生産数は、1945年の終戦までの間に、611万7847丁を数えました。これは同時期のガーランド自動小銃の生産数398万5404丁の1.5倍にも上り、アメリカ軍の火器で最も多く生産されることになりました。
参考文献
- Lieut. Col. Rene R. Studler. “A New Light Rifle : A Semiautomatic Carbine to Replace the Pistol and Submachine Gun”. Army Ordnance, vol.XXII, no.128, September-October 1941, pp.225-228.
- Lieut. Col. Rene R. Studler. “The New Semiautomatic Carbine : The Army Adopts a Light Rifle in Recors Time”. Army Ordnance, vol.XXII, no.130, July-February 1942, pp.570-571.
- Pete Kuhlhoff. “Light Weight Carbine : Increases Army’s Fire Power”. Popular Science, vol.140, no.6, June 1942, pp.79-80.
- War Production Board. Official Munitions Production of the United States by Months, July 1, 1940-August 31, 1945. Civilian Production Administration, 1947.